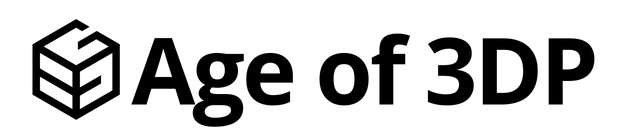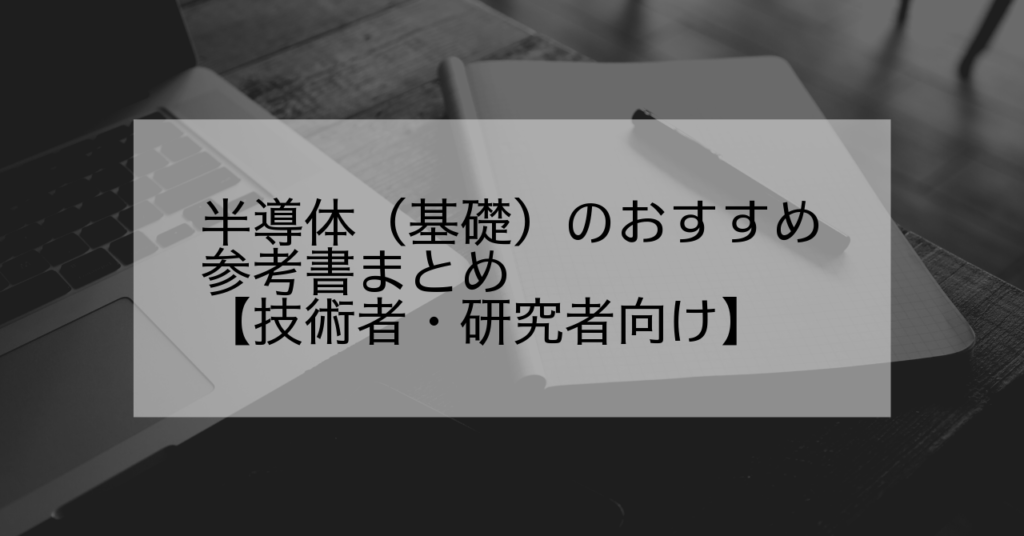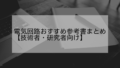こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は、技術者・研究者向け半導体(基礎)についてのおすすめ参考書(大学以降レベル)を紹介していきます。
私が半導体の基礎について学び始めた当初、ちょうどよいレベルの参考書探しに苦労しました。物性について深く学べる書籍から、半導体の学習にピンポイントな参考書まで様々なので、目的に応じた参考書選びが重要かと思います。同じような悩みをお持ちの方の参考情報となれば幸いです。
それでは見ていきましょう!
半導体(基礎)のおすすめ参考書まとめ【技術者・研究者向け、大学以降レベル】
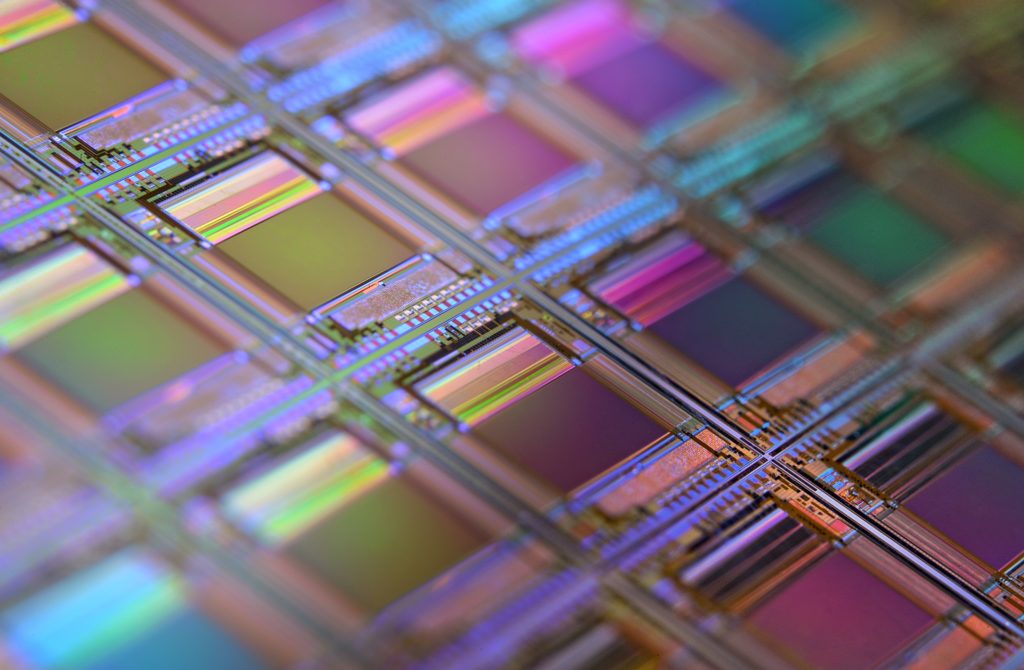
半導体デバイス入門―その原理と動作のしくみ
| 著者情報 | 柴田直/東京大学名誉教授(刊行時) |
| 発売日 | 2014/10/1 |
| 内容 | 第1章 デバイスの概念 第2章 結晶中の電子の振る舞い 第3章 半導体中の電子とホール 第4章 半導体中の電気伝導 第5章 PN接合 第6章 金属と半導体の接合 第7章 バイポーラトランジスタ 第8章 MOSトランジスタ 第9章 パワー半導体デバイスの考え方 |
| ポイント | ・半導体デバイスの基礎についてピンポイントで過不足なく学べる良書。 今回紹介する書籍の中では初学者に最もオススメ。 |
半導体の物理[改訂版]
| 著者情報 | 御子柴宣夫 |
| 発売日 | 1991/11/1 |
| 内容 | 1 固体の結晶構造と格子欠陥 2 固体の格子振動 3 固体のバンド理論 4 固体中の電子の統計分布 5 固体中の電子の伝導現象 6 半導体中の電子の散乱過程 7 半導体中の高電界効果 8 半導体界面の物理 9 半導体の光吸光 10 半導体発光の物理 11 半導体における非線形光学 12 ランダム系の物理 13 1次元電子系の物理 14 メゾスコピック系の物理 |
| ポイント | ・固体物理の基礎から始まり、半導体中のキャリアの伝導や界面の物理といった半導体物理の基礎、 光吸収や発光などの光物性まで含まれています。 基礎事項からさらに一歩深い内容まで学びたい方におすすめ。 |
キッテル 固体物理学入門 第8版<上>
| 著者情報 | チャールズ キッテル |
| 発売日 | 2005/12/1 |
| 内容 | 1 結晶構造 2 波の回折と逆格子 3 結晶結合と弾性定数 4 フォノンI:結晶の振動 5 フォノンII :熱的性質 6 自由電子フェルミ気体 7 エネルギーバンド 8 半導体 9 フェルミ面と金属 10 超伝導 |
| ポイント | ・固体物理学の定番参考書の上巻。 ・結晶やフォノンといった半導体に限定されない固体物理の基礎から始まり、超伝導にも及びます。 半導体のみならず、固体物理の基礎から学びたい方にオススメです。 |
キッテル 固体物理学入門 第8版<下>
| 著者情報 | チャールズ キッテル |
| 発売日 | 2005/12/1 |
| 内容 | 11 反磁性と常磁性 12 強磁性と反強磁性 13 磁気共鳴 14 プラズモン,ポラリトン,ポーラロン 15 光学的過程と励起子 16 誘電体と強誘電体 17 表面と界面の物理学 18 ナノ構造 19 非晶質固体 20 点欠陥 21 転移 22 合金 |
| ポイント | ・固体物理学の定番参考書の下巻。 ・下巻では磁性や光学的な内容が豊富です。 上巻以上に固体物理をシッカリ学びたい方にオススメです。 |
固体物理の基礎(上・I) 固体電子論概論
| 著者情報 | N. W. アシュクロフト N. D. マーミン |
| 発売日 | 1981/1/1 |
| 内容 | 第1章:金属のドゥルーデ(Drude)理論 第2章:金属のゾンマーフェルト理論 第3章:自由電子モデルの破綻 第4章:結晶格子 第5章:逆格子 第6章:X線回折による結晶構造の決定 第7章:ブラベー格子の分類と結晶構造の分類 第8章:周期ポテンシャル中の電子状態、一般的性質 第9章:弱い周期ポテンシャルの中の電子 第10章:強く束縛された方法 |
| ポイント | ・キッテル同様、著名な固体物理の古典アシュクロフト/マーミンの第1巻。 本巻では結晶や格子といった固体物理を深く学ぶ上では必須の内容について記述されています。 ・キッテルの方が固体物理の定番とされている印象がありますが、人によってはアシュクロフト/マーミンの方が分かりやすいという意見も多く聞かれます。 どちらを選ぶかは人によるかと思うので、図書館で軽く読んでみることをおすすめします。 |
固体物理の基礎( 上・II) 固体のバンド理論
| 著者情報 | N. W. アシュクロフト N. D. マーミン |
| 発売日 | 1981/1/1 |
| 内容 | 第11章:バンド構造を計算する他の方法 第12章:電子の動力学の半古典的モデル 第13章:金属伝導の半古典的理論 第14章:フェルミ面の測定 第15章:いくつかの金属のバンド構造 第16章:緩和時間近似を越えた近似 第17章:独立電子近似を越えた近似 第18章:表面効果 |
| ポイント | ・アシュクロフト/マーミンの第2巻。 金属のバンド構造に関する記述が主題となっています。 |
固体物理の基礎( 下・I) 固体フォノンの諸問題
| 著者情報 | N. W. アシュクロフト N. D. マーミン |
| 発売日 | 1981/1/1 |
| 内容 | 第19章:固体の分類 第20章:凝集エネルギー 第21章:静止格子模型の破綻 第22章:調和結晶の古典論 第23章:調和結晶の量子論 第24章:フォノン分散関係の測定 第25章:結晶の非調和効果 第26章:金属中のフォノン 第27章:絶縁体の誘電的性質 |
| ポイント | ・アシュクロフト/マーミンの第3巻。固体の種類の分類にはじまり、各種結晶についての議論、そしてフォノンに関する内容が主題となっている。 |
固体物理の基礎( 下・II) 固体の物性各論
| 著者情報 | N. W. アシュクロフト N. D. マーミン |
| 発売日 | 2008/7/1 |
| 内容 | 第28章:均質な半導体 第29章:不均質な半導体 第30章:結晶中の欠陥 第31章:反磁性と常磁性 第32章:電子相互作用と磁気的構造 第33章:磁気的秩序 第34章:超伝導 |
| ポイント | ・アシュクロフト/マーミンの第4巻。 半導体や磁性体、超伝導体について記述されており、今回の記事におけるおすすめは半導体を主題として扱うこの第4巻となります。 ・磁性体、超伝導体については概論程度なので、これらの内容に興味がある場合は他の専門書を併読すると良いでしょう。 |
参考書を活用して半導体の基礎を学ぼう
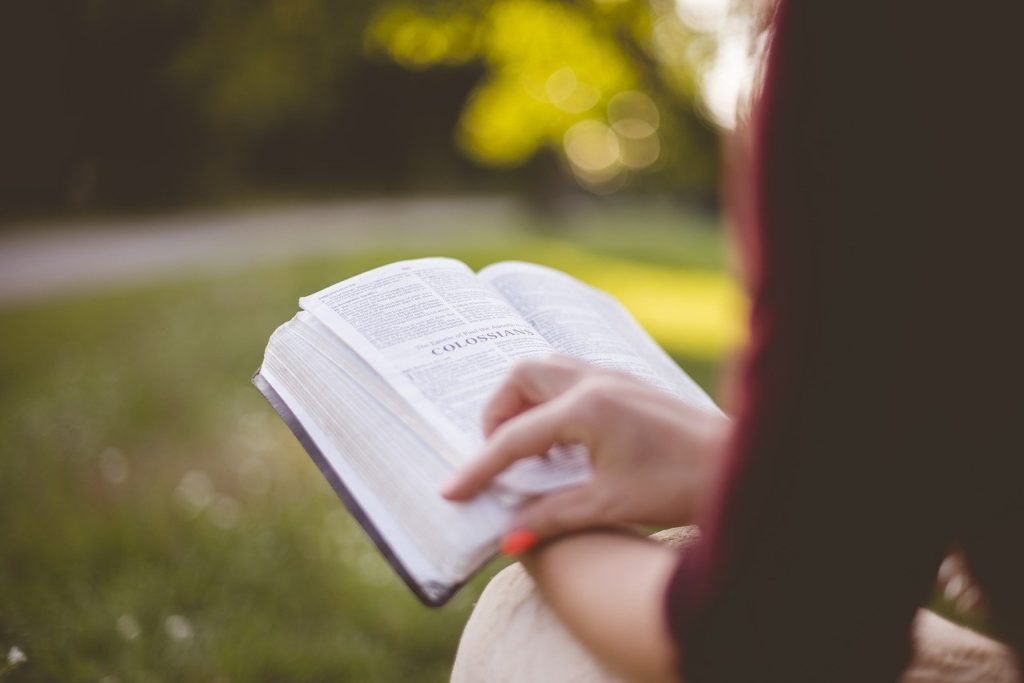
今回は、技術者・研究者向けの半導体の基礎について学べる参考書について紹介してきました。
半導体の理解には固体物理に関する知識が欠かせません。そのため半導体単体で学ぶのは難しく、キッテルやアシュクロフト/マーミンを適宜参照する道は避けて通れないのではないかと感じます。
一方で、「半導体デバイス入門」「半導体の物理」は最低限物性の基礎を学ぶことができ、かつ半導体の基礎が充実した良書です。最短距離で半導体を学びたい方はこれらの参考書を使って半導体の世界に足を踏み入れるルートもアリかと思います。