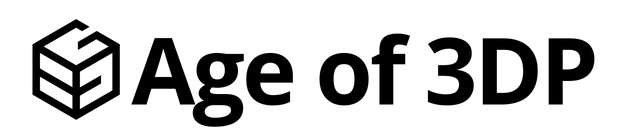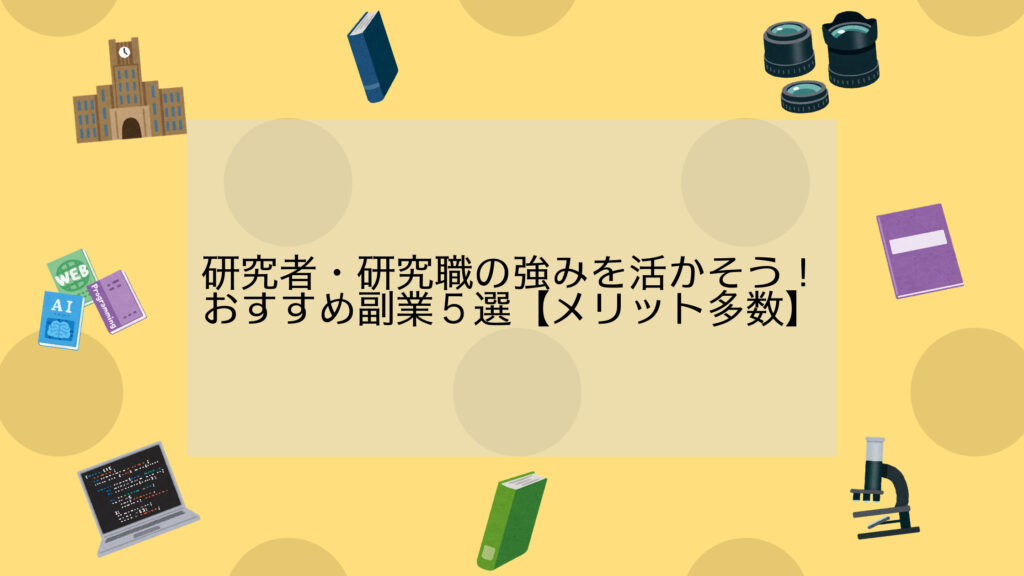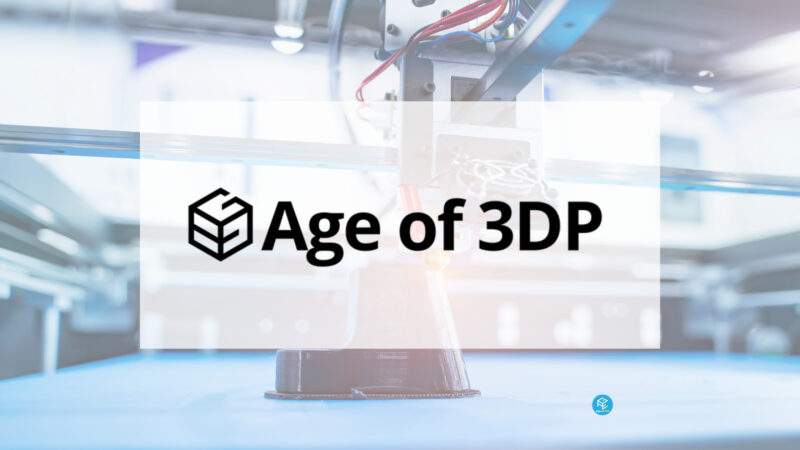こんにちは、管理人のウノケンです。
今回は研究者・研究職の強みを活かせる副業5選を紹介していきます。
「副業解禁」や「老後2000万円問題」等で注目されている副業。研究者・研究職、そして研究に励む大学院生の中にも、副業に興味を持っている方は多いのではないでしょうか?
今回は、研究者・研究職ならではの強みを活かしたおすすめの副業を5つ紹介します。さらに、「忙しい研究者が副業をするメリット」や、「副業をする際の注意点」、「副業をする時間がない人が考えるべきこと」についても解説していきます。
ポイントを押さえてあなたも副業にチャレンジしてみましょう。
- 研究者が副業をするメリットを知りたい方
- 研究者の強みを活かせる副業の種類について知りたい方
- 研究者が副業をする際の注意点について知りたい方
研究者が副業をするメリット

そもそも研究者が副業をするメリットにはどのようなものがあるでしょうか?
副業と聞くと「お金を稼ぐ」ことがイメージされがちですが、メリットはそれだけではありません。
「お金を稼ぐ」以外のメリットも含めて解説したいと思います。
収入基盤が強化される
まずは収入面です。期限付きの雇用形態の場合や若手の時期など、収入が心もとない場合も多い研究者。本業以外の収入源が1つでもあると、心のゆとりに繋がります。心に余裕があると生活を過度に気にする必要がなくなり、研究に打ち込むことができます。
本業で役に立つ
副業に取り組むことで、本業でも役に立つ以下のような能力が身につく場合もあります。
- 情報収集能力
- プログラミング能力
- コミュニケーション能力
それ以外にも、副業を通して広がった人脈を本業に役立てることも可能でしょう。
本業(研究)と副業の相乗効果によって双方にポジティブな影響を与えられることが、副業の大きなメリットの1つです。
人の役に立つ
「研究」という仕事は人の役に立つまでに長い時間がかかります。芽が出なかった場合には、世間の人々にその研究自体が知られないということも少なくありません。
副業の種類によっては、困っている人の役に立つことが可能です。詳しくは後述する具体例で述べますが、研究者がもつ経験や技能、専門知識は想像以上の需要があります。副業によって、本業では感じにくい「他人の役に立った」という感覚が得られるのは「副業をやって良かった」と感じられるポイントでしょう。
研究者の強みを活かせる副業5選

「お金を稼ぐ」以外にもメリットの多い副業。ここからは、研究者におすすめの副業について解説していきます。
「副業なんてやったことないし、うまくいかないのでは…?」と思う方も多いことでしょう。
そんなあなたに意識してほしい副業成功の鍵は、「研究者としての強みを活かす」ことです。
ビジネスの基本は「他者に価値をもたらすこと」です。副業とはいえ立派なビジネスですから、「研究者としての自分が他者にもたらせる価値とは何か?」を突き詰めることが必要です。
研究者としての強みを活かしやすいポイントには次のようなものがあります。
- 経験
- 受験、留学、就活の経験を発信する
- 専門分野
- その分野に興味がある人に向けて情報発信する
- 英語力・プログラミング力
- 英語力やプログラミング能力が活用できる、翻訳や開発の案件を受注する
- 勉強法について情報発信する
他にも研究分野や環境によって、活かせる能力は様々です。他の人にはない自身の強みは何か、副業をスタートする前に考えてみましょう。
さて、以上のポイントを踏まえ、研究者の特徴を活かせる副業7選について解説していきます。
ブログ
まず最初に紹介するのは「ブログ」です。ブログをおすすめする理由は次の通りです。
- ノウハウが蓄積されているためスタートしやすい
- ストック型である
- 初期費用・ランニングコストが小さい
「副業」と聞いて「ブログ」をイメージする方も多いでしょう。実際に研究者に限らず多くの方がブログによって収益をあげています。
ブログ自体は歴史があり、はじめ方や困ったときにどうすればよいかということが、調べるとすぐに解決できます。ブログは開始するためのハードルが低く、忙しい研究者であっても安心してスタートすることができます。
また、「ストック型」である点もメリットの1つです。「ストック型」というのは、継続的に収益を上げられるビジネスモデルのことです。アルバイトのような「フロー型」の副業と異なり、「時間の切り売り」になりにくい点が「ストック型」の副業の特徴です。研究者としての経験・技術を発信した記事が「ストック」され、継続的に収益を上げられる可能性があるのです。
また、副業のメリットに挙げた「人の役に立つ」という点でも、ブログは活躍します。私の例では、書籍の紹介によって著者の方に喜んでもらえた経験が心に残っています。
以下のツイートは、PyTorch初心者のおすすめ書籍【PyTorch実践入門】で学べることという記事を公開した際に、翻訳者の小川雄太郎さんにリツイートしていただいたときのものです。
自分が勉強に使用した書籍を紹介した記事が、翻訳者本人の目に触れて喜んでもらえたのです。
このような経験は、本業の研究で得るものとは違った充実感があります。「本業では得られない体験ができること」は、副業をするメリットの1つなのではないかと思います。
初期費用・ランニングコストが低いのもブログのメリットです。ブログ運営に必要なコストはドメイン・レンタルサーバー代が主で、ひと月あたり1000円程度で済んでしまいます。運営によって得られるメリット・収益を考えればかなり良心的であると言えるでしょう。
ブログのおすすめ度:
ブログのはじめ方については、こちらの記事をご参照ください!
YouTube
YouTubeも研究者が強みを発揮できる副業の1つとして外せないでしょう。YouTubeはエンタメだけでなく学習用途でも需要の多いプラットフォームです。
研究に近い教育系YouTuberの例としては、ヨビノリたくみさんなどが有名ですね。登録者数はおよそ70万人(2021年5月現在)、書籍も刊行するほどの人気ぶりです。他にも大学院生・研究者がYouTubeを始める例は増えています。試しにYouTubeで「大学院生」と検索してみてください。
YouTubeをおすすめする理由は次の通りです。
- スマホ1つで始められる
- 基本的にランニングコストゼロ
- ストック型である
- 動画で学びたいという需要が伸びている
カメラやマイクに専用の機材を使わなくても、今やスマホ1つで十分配信可能なクオリティの動画が撮影できます。PCを介さずに動画を投稿することも可能です。費用もかかりません。
また、YouTubeもブログ同様「ストック型」のビジネスです。需要のある動画を自身のチャンネルに蓄積していくことで、広告収益を継続的にもたらしてくれる可能性があります。
5Gの時代が到来し、「動画で学ぶ」というのはもはや当たり前の時代となっています。研究者が自身の研究発表などで培ったプレゼン技術をもとに、専門知識・技能を発信していくことは、まさに研究者の強みを活かした副業であると言えるでしょう。
YouTubeを始める場合、画質・音質を追求したり、編集に時間をかけるのは、ある程度登録者数が増えてからで良いでしょう。始めから力を入れすぎると、登録者数が伸びなかった場合にやる気が削がれる原因になります。簡単な動画編集であれば無料のアプリでも十分可能です。Macの「iMovie」なども優秀なのでぜひ使用してみてください。
動画投稿に慣れ、ある程度登録者数・再生回数が増えてきたら、力の入れ時です。高音質なマイクや動画編集ソフトを購入し、内容以外の面でも動画のクオリティを上げていきましょう。
YouTubeのおすすめ度:
note、電子書籍販売
noteや電子書籍の販売も、研究者の知見を発信し、収益を得る手段の1つです。
noteや電子書籍の販売をおすすめする理由は次の通りです。
- 気軽にスタートしやすい
- 広告収入とは異なり、自身で単価を設定できる
- 広く知られていない情報発信によるニッチ需要を取り込める
noteとは、「クリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォーム」(note公式より)です。
「研究者の副業となんの関係があるの?」と思われるかもしれません。noteを副業とする手段は、「有料記事販売」や「定期購読マガジン配信」です。ユーザが購入したいと感じる価値のある内容を有料記事として販売することで収入を得る副業モデルです。定期購読マガジンの読者を獲得できれば、継続して収入を得ることも可能です。
「自分がもっている知識・経験をにお金を払ってくれる人なんているの…?」と思う方も多いでしょう。1つ言えることは、先輩研究者の知見は貴重だということです。というのも、特定の研究機関や研究分野に関わる情報はクローズドな場合が多く、あまり公開されてない有益な情報が多いからです。
もちろん、機密情報を公開することはできませんが、「公開される機会がなくてあまり知られていないけど、組織や環境に関心のある人が知りたい情報」というのは意外に需要があります。自身の後輩や少し離れた立場にいる知人に、「どのような情報だったら少額のお金を払ってもいいと思うか」リサーチしてみるのも良いでしょう。
例えば、「海外の○○大学に留学した経験」や「海外の研究機関で研究した際の体験」などには、興味を示す方が一定数いるのではないかと思います。記事の価格が500円であっても、20人が購入すれば10,000円になります(別途手数料がかかります)。副業としてはまずまずの金額ではないでしょうか?
noteの他に、「電子書籍として出版」する方法もあります。いまや、驚くほど短時間で、簡単に世界中の人に書籍を届けることができる時代になっています。有名なものはAmazonの「Kindle direct publishing」でしょう。出版までのノウハウもネット上に豊富に存在するので、気になる方は検索してみてください。
どちらも優れた発信プラットフォームですが、気軽に短めの内容を発信するのにはnote、まとまった内容を書籍化するのであれば電子書籍として出版という使い分け、あるいは読者層に応じた使い分けをすると良いでしょう。
note、電子書籍販売のおすすめ度:
クラウドソーシング
こちらも副業の有力な選択肢として有名な「クラウドソーシング」です。
クラウドソーシングとは、「不特定多数の人の寄与を募り、必要とするサービス、アイデア、またはコンテンツを取得するプロセス」(Wikipediaより)のことです。「特定の技能をもつ人に対して、企業や個人が仕事を発注するシステム」と考えるとわかりやすいでしょう。
- プログラミングや英語の技術を活かせる
- 研究・教育関連のサポートといった、企業が手を出しにくいニッチな案件もある
- 研究者としてのスキルを出品できる
- ブログ・YouTube等に比べて即金性が高い
研究職の副業探しでおすすめなクラウドソーシングのプラットフォームとしては、「クラウドワークス」や「ランサーズ」などが挙げられます。どちらもクラウドソーシングの業界最大手であり、初心者でも始めやすいです。
「Web開発」や「アプリ制作」のようなプログラミング力を活かせる案件、「翻訳・通訳」といった英語力が活かせる案件が豊富な点も注目ポイントです。
クラウドワークス

>> 公式サイトはこちら「CrowdWorks(クラウドワークス)」
ランサーズ

>> 公式サイトはこちら「ランサーズ」
ココナラ

また、スキルを売買できるプラットフォーム「ココナラ」も伸びています。
クラウドワークスやランサーズとの大きな違いは、「案件の獲得方法」です。クラウドワークスやランサーズでは基本的に依頼主の案件に応募する形であるのに対し、ココナラでは「スキルを出品」し、お客側がそれを購入するという形になっています(お客側の依頼に応募する形式も存在しますが、メインは「スキルの出品」です)。
クラウドワークスやランサーズと同様の「プログラミング」や「翻訳」のようなカテゴリはもちろんのこと、ココナラには次のような「研究職の強み」を活かせる出品カテゴリがあります。
- 勉強・学習方法の相談
- 受験の相談
- 就職活動(新卒)の相談
- 留学の相談
実際に出品されている、「研究職」の方による出品例を見てみましょう(2021年5月8日現在)。
- 「大手メーカー研究員が研究職のESを添削します」
- 単価:4,000円
- 販売実績:58件
- 「Fortran/Matlabコードの相談承ります」
- 単価:4,000円
- 販売実績:83件
- 「科研費・研究費の申請書アドバイスします」
- 単価:10,000円
- 販売実績:46件
ユニークなスキルが出品されていることがわかりますね。「研究職ならでは」の意外なスキルも見られます。「自分のスキルも売れるかも…?」と感じた方も少なくないでしょう。他にもいろいろな出品例があるので、ぜひ検索して「どのようなスキルが」「どれくらい」売れているのかチェックしてみてください。
ココナラを副業として活用するためには、「自分のどのようなスキルに需要があるのか?」という点を吟味する必要があります。逆に言えば、出品できるスキルの提案は自分次第であり、可能性は無限大です。自身の経験・技術を棚卸しして、「どのように人の役に立てられるか?」を見極めることが成功の秘訣です。
最後に、クラウドソーシングの注意点を挙げておきます。それは、「フロー型」の副業になる点です。本業と平行して行う以上、「時間を切り売りする」ことには注意が必要です。本業に支障をきたすようでは元も子もありません。副業に割くことができる時間を考慮した上で取り組みましょう。自身のキャリアにプラスに働くような案件を獲得できるケースであれば理想的です。
クラウドソーシングのおすすめ度:
スマホアプリ開発
最後に紹介するのは、「スマホアプリ開発」です。スマホアプリ開発のおすすめポイントは以下の通りです。
- プログラミング能力を活かせる・勉強にもなる
- 自分がほしいアプリを作れるようになり、楽しく開発できる
スマホアプリ開発で収入を得る主な方法は次の2つです。
- 有料アプリとして出品する
- アプリ使用時に表示される広告から収入を得る
「スマホアプリなんて作ったことない!」という方でも、ちょっとしたアプリであれば簡単に開発することができます。研究を通して少しでもプログラミング経験があれば問題ありません。参考書1冊程度の勉強で十分開発を始めることができます。
スマホアプリ開発で副業収入を得るポイントは、「企業が参入していないニッチな分野で需要のあるアプリを開発する」ことです。企業がコストをかけて開発するようなアプリに個人で対抗するのは現実的ではありません。一方、企業が参入しないような領域にはチャンスがあります。潜在需要を上手く探し当てることができれば、多くのユーザにアプリを購入してもらったり、広告収入を得ることも可能です。
スマホアプリ開発のおすすめ度:
副業をする際の注意点

ここまで、研究者・研究職の強みを活かせる副業のメリット・種類を紹介してきました。
最後に、副業を開始する際の注意点を確認しておきましょう。
会社・組織の規定を守る
当然ですが、会社や組織に属している以上、その規定を守って副業をすることが求められます。具体的には以下の点に注意しましょう。
- 副業が禁止されていないか?
- 会社の機密保持に反していないか?
会社によって副業に関する規定は異なるので、就業規則をチェックしておきましょう。
本業をおろそかにしない
また、副業に精を出すあまり、本業に支障が出ては元も子もありません。本業がおろそかになったり、働きすぎて身体を壊さないように注意しましょう。
本業が忙しくて副業する時間がない!そんなときは…
「副業には興味があるけど、本業が忙しくて副業の時間は取れない…」
そんな方は、一度自身の職場環境を見直してみましょう。副業ができないほど本業が忙しいのは、そもそも職場の風土・働き方に問題がある可能性があります。
世の中には、同じくらいの業務量・アウトプットでも高い給料を支払ってくれる会社が思っているよりも多いです。とくに、新卒から年功序列の日本企業で働く人は市場価値に見合った給料をもらえていない可能性があります。
同じアウトプットでもより多くの年収を稼いでいる人は、転職によって自身の市場価値のメンテナンスを行っているのです。「ひょっとしたら自分の年収は働きに見合ってないかも…?」と感じている人はぜひ一度転職エージェントを活用してみましょう。転職エージェントの利用は基本的に無料(会社側がお金を払うシステム)ですし、仮に今すぐ転職する気はなかったとしても転職活動自体にリスクはありません。転職エージェントを使ってみて、今よりも高い年収の企業が見つかればラッキーですし、見つからなければ転職しなければよいのです。
ひとくちに転職エージェントといっても、世の中にはたくさんのエージェントがあります。満足のいく転職活動を進めるためにも、【アカリクキャリア】のような研究職案件に強い転職エージェントを活用しましょう。

研究職の強みを活かした副業にチャレンジしてみよう
今回は研究者・研究職の強みを活かせる副業5選について紹介してきました。
- ブログ
- YouTube
- note、電子書籍販売
- クラウドソーシング
- スマホアプリ開発
自身の「研究者としての強み」を活かして、ぜひ副業にトライしてみてください!